教育・ハウツー
-

新型コロナ、片付け、トイペ騒動、そして備蓄
新型コロナウィルスの影響で、出演予定だったライブやイベントが中止になっています! ということで、こんな時でないとなかなかできない片付けをしているのですが、友人宅の片付けに訪れたら、やっぱりトイレットペーパー騒動に巻き込まれていました! なるほど、こんな時だから、常日頃の備蓄についてちょっくら再考するのもいいかもです!
2020/03/09
-

世界に広がる新型コロナウイルス感染
鳥インフルエンザの予定を変更し、新型コロナウイルスについての考察をお届けします。コロナウイルスは動物から人への感染が成立してから時間を経ていないため、人に感染したウイルスの動態が詳しく分かっていません。筆者は1970年代初めから鳥類のコロナウイルス感染による「鶏伝染性気管支炎(IB)」の研究に取り組んできました。COVID-19とは近縁ではありませんが、同じコロナウイルスであることから、興味深い共通点が見つかるはずです。
2020/03/06
-

新型コロナウイルス騒動で中国もBCPに着目!?
上海市では、日本からの入国者に14日間の経過観察を求める方針を日本総領事館に通知しました。感染の「拡大」抑制から「逆流」防止へ新たな対策がとられ始めたといえますが、旅行業や交通業などへの経済的影響は大きく、事業継続に関わる事態も。単なる騒動では済まされない状況に至り、中国でもBCP(事業継続計画)への関心が高まりそうです。
2020/03/06
-

第25回:災害時の帰宅または移動の留意点
大災害の発生時には、公共交通機関の停止や道路の寸断などにより大量の「帰宅困難者」が発生する。とくに大都市の企業においては、こうした帰宅困難者に対する備えは必須だ。内勤、外勤それぞれの社員に対する備え、訪問客に対する備え、そしてどうしても帰らなければならない場合への備えは、十分だろうか。
2020/03/05
-

水なしで戻せる!簡単切り干し大根とツナのサラダ
乾物は手間がかかるイメージですが、ほとんどは加熱しなくても食べられます。最近はカットされたものや小分けタイプもあり、より使いやすくなっていますので、ぜひつくってみてください! 水や火を使わず手も汚れないうえ、栄養価が高く、お子さまから高齢者の方にも柔らかく食べやすいメニューです!
2020/03/05
-

第14回:火災発生後の初動対応
火災は、地震や水害などの自然災害に比べると、より身近なリスクであるといえます。また、さまざまな防火対策を講じることによって火災の発生頻度を下げることは可能ですが、その頻度をゼロにすることはできません。今回は、実際に火災が発生した際の初動対応について考えます。
2020/03/04
-

【Lesson1(3講義)】新型コロナウイルス対策における法的な注意点を知ろう
新型コロナウイルスを中心とした感染症対策で考えておくべき法的な対応について解説します。解説者は、丸の内総合法律事務所の弁護士・中野明安氏です
2020/03/02
-

新型肺炎の拡大が止まらない!どうする3月からの株主総会?
新型コロナウイルスの感染拡大により、大規模イベントどころか、小規模なセミナーや日常的な会議までもが自粛されてきているが、3月からは企業の株主総会が始まる。企業はどう対応すればいいのか、丸の内総合法律事務所の中野明安弁護士に特別寄稿いただいた。
2020/03/02
-

新型コロナウイルスで企業が考えるべきこと
新型コロナウイルスに関する政府の基本方針の発表を受けて、企業ではさまざまな対策を検討・実施しています。感染症の発生段階として、政府は現在「第二段階(国内発生早期)」との認識ですが、これが「第三段階(感染拡大期、まん延期)に移行してしまうのかは、この1~2週間が瀬戸際であるとの見解を示しました。
2020/02/28
-

第2回 リスクの保有と移転
欧米の企業では、リスク管理責任者(CROやリスクマネージャー)が置かれることが多く、企業保険の検討や手配はリスクマネージャーの業務の一つです。しかし多くの日本企業では、CROやリスクマネージャーどころかリスク管理統括部門すら存在しません。存在している場合でもBCPや危機対策などの限定的な領域を担当するだけで、経営の意思決定に関わることがあったとしても単なる認証機関という形式的な部門になっている企業が多いようです。
2020/02/26
-

非常口のピクトグラム
非常口のピクトグラムは、2種類あるということは知ってますか? 実は、非常口のピクトグラムは、背景が「緑色」と「白色」の2種類あります。皆さんは「背景が緑色」の方をよく見かけると思いますが、それぞれ違いがあるのです。
2020/02/25
-

ハラスメントへの注目が加速、最悪な状況も想定
ある日、あなたの会社の元社員が突然「会社から〇〇のハラスメントを受けた」として記者会見。これを受けメディアからの問い合わせが会社に殺到。どう対応したらいいでしょうか。具体的に考えてみましょう。
2020/02/21
-

第24回:安否確認のポイント
安否確認は、災害が発生した際に「利害関係者」が無事どうか、出社・帰社や移動は可能かどうかを尋ねる重要な作業です。しかしひと口に「利害関係者」といっても対象は多岐にわたり、被災時の状況も多様。コミュニケーション手段も一つではなく、必ずしも平時のツールが使えるとは限りません。「事前の備え」が重要です。
2020/02/20
-

現地報告 コロナウイルス騒動で右往左往する駐在員
今回は、中国に居住する者として、新型コロナウイルス騒動によって現地で何が起きているかをお伝えします。結論から申し上げますと、日本人駐在員の中で責任者と呼ばれる方々でさえ、しっかりした情報をとらえることができず、刻々と変化するさまざまな状況に翻弄されているのが実情です。
2020/02/19
-
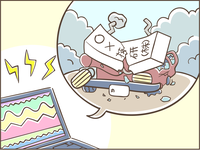
巨大災害時の共通のリーガル・ニーズを知っておこう
熊本地震は、地震や土砂災害で直接亡くなった方が50名であるのに対し、災害後に過酷な避難生活などが影響で亡くなった「災害関連死」が200名以上に及んでいます。原因のひとつは、東日本大震災における実績や教訓が熊本地震の現場に引き継がれなったこと。たとえば、東日本大震災における避難所環境改善の実績が災害救助制度に反映されなかったことで、自治体の備蓄や防災の知恵につながらなかったことは、残念でなりません。
2020/02/19
-

第13回:水害の初動対応
地震は突発型災害ですから、実際に地震が発生した後にその初動対応をスタートさせます。一方、水害は、いわゆる進行型災害です。例えば、台風が接近することにより強風や大雨が発生し、時が経過するにつれて高潮や洪水が起こるというパターンです。そこで、水害の発生によって起こり得る状況や被害を事前に関係者で共有し、時間の経過に応じた初動対応を進めることが重要です。
2020/02/19
-

世界の鳥類に拡大 人への感染に警戒
これまでの連載で、すべてのインフルエンザウイルスの祖先は鳥インフルエンザウイルスことを紹介してきました。しかし、罹患するのが主に鳥類のため、その病原性や病状、感染の状況については広く知られていません。鳥インフルエンザウイルスの基礎知識と、今後の人への感染のおそれについて解説します。
2020/02/19
-
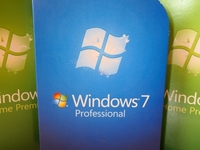
Windows 7利用者は要注意!
2020年1月14日をもって、Windows7のサポートが終了し、セキュリティ更新プログラムの提供が無くなりました。またOSだけでなくアプリケーション(ソフトウェア)も順次サポートが終了していきます。
2020/02/19
-

火災における犬と猫の救急医療判断と治療
住宅火災の現場で、あなたが最初の応急処置を行う人として遭遇したとします。家の持ち主は無事に避難していますが突然、消防士がぐったりした犬と一緒に家の玄関から出てきました。消防士は、あなたとあなたの応急処置を行った救急隊を見て、こちらへまっすぐに向かってきます。 消防士は、息はあるものの瀕死の状態の犬をあなたに手渡します。さあ、どうしたらよいでしょう?
2020/02/14
-

局面は水際対策から次のフェーズへ移行しつつある
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。2月10日時点で中国国内の感染者は4万人超、死亡者は900人を超え、2003年のSARSを上まわった。WHO(世界保健機関)は緊急事態を宣言し、日本政府も水際対策に躍起。乗客に感染者がみつかった大型クルーズ船は現在なお停泊中だ。いま何が起きているのか、これからどうなるのか。東京医科大学病院渡航者医療センター部長で東京医科大学教授の濱田篤郎氏に聞いた。※インタビュー本文は2月6日取材時点の情報にもとづいています。
2020/02/12
-

「支援制度があること」の周知自体が重要な支援
2011年3月、東日本大震災が発生した当初、弁護士もまた現場の被災者の声を聞き、少しでも役立つ情報を提供しようと必死になっていました。私は、この膨大な被災者の声を「視覚化」して、記録に残し、広く政策提言に活用すべきではないかと考えました。ひとりの弁護士として日弁連にかけあい、2011年4月から日弁連の災害対策本部室長として相談事例の分析を担うことになりました。
2020/02/12
-
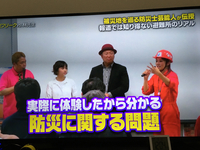
赤プル、テレビで緊張する!
ここ最近、立て続けに「防災芸人」としてTV番組でご紹介いただく機会がありました。もちろん嬉しい! のですが、妙な緊張感も正直ありました(汗) ネタ番組やトーク番組は優秀な作家さんやディレクターさんにめちゃくちゃ愛のある編集をいただくことも多く、感謝することが多いTVなんですけれど、テーマが「防災」ということで、一瞬、怯んでしまいました。
2020/02/07
-

色と多言語表記を考える
この連載では、防災や危機管理におけるピクトグラムを使ったコミュニケーションについて、ピクトグラムのメリットとデメリットを、具体的な事例を用いながら解説し、効果的なピクトグラムを使った表現方法を考えてみたいと思います。ピクトグラムのメリットは、事前の学習や特別な知識がなくても理解できることです。文字を使わなくても、見て直感的に情報を伝えられる視覚記号(サイン)なので、目の見えづらくなった高齢者、漢字が苦手な子ども、外国人、一部の障害者など文字の読めない人にも情報を伝えられることです。
2020/02/07
-

台風19号災害 大規模避難、地域貢献、そして地域包括BCP
長野県長野市豊野町の社会福祉法人賛育会と豊野事業所は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウス、訪問介護事業所、ディサービスセンター、訪問看護、通所リハビリテーション、クリニック等を有する大規模法人。台風19号で大きな被害を受けたが、一人の人的被害もなく避難を行い、また応急対策時にはNPO等と連携してボランティアセンターの運営支援、炊き出しなど地域貢献活動を展開している。賛育会事務長の松村隆氏にお話を伺った。
2020/02/07
-

第23回:従業員の命を守るとはどういうことか?(2)
「激しい台風や豪雨の際は、新聞販売店では配達よりも従業員の安全確保を最優先する」。こうしたメッセージを新聞社または折込広告会社が発信するということは、悪天候時の配達の是非を新聞販売店の判断に一任するということ。では、最終的な意思決定者である新聞販売店では、配達員が安全に配達できるような仕組みを独自につくることは可能だろうか。
2020/02/06




















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



