自然災害
-

被災地の活動団体に災害用無線機をレンタル
防災用機器製造・販売のテレネットは、能登半島地震の被災地で復旧活動を行う自治体や企業に災害用無線機とモバイルルータをレンタルしています。復旧支援に少しでも役立てばという思いで始めた取り組み。これまでに、2種の機器合わせて、延べ16団体に90台を貸し出しました。
2024/03/13
-

地域の防災力向上に貢献する防災備蓄最適化サービス
BELLグループのmilabは、地域のステークホルダーが平時の段階から災害時を想定して助け合いながら、防災力向上に貢献するための防災備蓄最適化サービス「SMART STOCK」を提供する。自治体向けの「SMART STOCK for Government」、企業向けの「SMART STOCK for Enterprise」、マンション向けの「SMART STOCK for Mansion」の3つを展開する。
2024/03/12
-

能登の復興は日本のこれからを問いかける
半島奥地、地すべり地、過疎高齢化などの条件が、能登半島地震の被害を拡大したとされています。しかし、そもそも日本の生活基盤は地域の地形と風土の上に築かれ、その基盤が過疎高齢化で揺らいでいるのは全国共通。金沢大学准教授で石川県防災会議震災対策部会委員を務める青木賢人氏に、被害に影響を与えた能登の特性と今後の復興について聞きました。
2024/03/10
-

ESGによって見直しが迫られるリスク管理
将来の企業価値に影響を及ぼす非財務要素(ESG)の台頭により、リスク管理が新たな局面を迎えている。企業が今後の重要テーマである気候変動リスクや生物多様性リスクについて検討する場合において、改めてERMの機能や構造を検証することが重要と考えられる。
2024/03/09
-

仕掛けと工夫がなければ舞台はまわらない
BCPで規定した計画と現実との間のギャップを抽出し、多くの企業に共通の「あるある」として紹介、食い違いが生じる原因と対処を考える本連載。第2章では「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。前回に続き、今回もBCPの実効性に関連して初動・災害対策本部の「あるある」を取り上げます。
2024/03/08
-

企業の自衛消防隊が最低限知っておくべき消防知識(中級編)~実際に活動できる自衛消防隊にしよう~
4月10日15時から、自衛消防隊向けの特別セミナー(中級編)を開催します。実際に活動できる自衛消防隊になっているか見直す内容となっています。講師は、元西宮市消防局北消防署長の長畑武司氏(一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会 事務局次長兼点検推進指導員)です。
2024/03/07
-
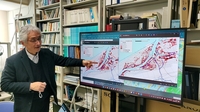
造成地や砂丘地域に液状化被害が集中した新潟市国や自治体のハザードマップ活用を
能登半島地震では、震源地から離れた新潟県新潟市で震度5強を記録した。新潟市の被害で顕著だったのが液状化だ。砂の吹き出した痕跡がそこかしこに見られ、地面の陥没、盛り上がりが多数発生。多くの住宅が影響を受けた。液状化を専門とする新潟大学助教の保坂吉則氏に新潟市の液状化について聞いた。
2024/03/07
-

バンダイナムコエンターテイメント流、人を魅了する情報の伝え方
2024年2月の危機管理塾は3月12日16時から行います。今回の発表者は、バンダイナムコエンターテインメントの岡部健也氏です。
2024/03/05
-

過酷な環境での運用に耐えられるウェアラブルカメラ
i-PROは、最長12時間の連続運用が可能で、堅牢性、操作性、信頼性を備えたウェアラブルカメラ「WV-BWC4000UX」を販売する。北米の警察で多数の導入実績があるウェアラブルカメラと同じハードウェアを採用しており、保安・警備業務など、過酷な環境での運用に耐えられるように設計されたもの。
2024/03/02
-

縮小へ向かう社会のよりよい復興とは
能登半島地震が浮き彫りにした地域の衰退。しかしそれは能登に限ったことではありません。本格的な人口減少時代に入るといわれる日本で、右肩上がりの復興をイメージすることはもうできないでしょう。縮小に向かう社会において、よりよい復興とは何か。専門家・実務者のインタビューと独自調査から探ります。
2024/03/01
-

充実する災害情報いかに整理して見せるか
政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」は、2030 年度までの全自治体のデジタル実装が目標。交付金制度を活用した事業の採択も増え、防災DXサービスにも追い風が吹いています。災害時の情報共有システムを提供するブイキューブ公共ソリューション営業グループの武井祐一氏に、防災DXサービスの動向と今後を聞きました。
2024/03/01
-

燃えやすい木密地域で消火活動が困難に
2024 年の幕開けを襲った能登半島地震。輪島市の朝市通り周辺で発生した火災は、消火できずに拡大する延焼が中継され、地震火災の恐ろしさを突きつけました。日本火災学会の調査として現地に入った東京大学先端科学技術研究センター教授の廣井悠氏に、輪島市の大火について聞きました。
2024/03/01
-

ドローン配送のGNSSスプーフィング対策実証に成功
国産の産業用ドローンの開発を行うACSLはこのほど、2024年度に導入される予定の準天頂衛星システム「みちびき」による信号認証サービス(航法メッセージ認証)に対応した国産ドローンの開発に向けて、コア、楽天グループの2者との共同実証実験を実施した。ドローンを本来とは違うルートに誘導する“GNSS (全地球航法衛星システム)スプーフィング(なりすまし)”への対策として、測位信号の真正を検証できる仕組みを提供する同サービスを利用したドローン航行を実証するもの。
2024/02/28
-

現場の声を反映した「タフネス仕様」リストバンド型メモ
機能性フィルムの開発から品質保証までの総合ソリューションを提供するコスモテックは、「いつでも、どこでも、書ける、思い出せる」を基本理念に展開するB to C向け製品のウェアラブルメモ「wemo(ウェモ)」シリーズから、現場最前線の要望を反映して開発した「タフネス仕様」のリストバンド型メモ「wemo PRO バンドタイプ」を販売する。
2024/02/28
-

製造後7年の長期保存が可能な災害備蓄用カイロ
エステーは、非常時や災害時の備蓄品として、製造から7年の長期保存ができる、貼らないタイプの「オンパックス 長期保存カイロ」を販売する。グループ会社のエステーPROの業務用ルートやオフィス向けカタログ通信販売ルートを通じて、官公庁、一般企業、自治体などに向けて販売する。
2024/02/28
-

能登半島地震における企業の対応レジリエンスの実現に向けて
脆弱性を突いて発生した能登半島地震は、極めてシリアスな被害様相を見せつけました。防災・BCPの何が機能し、何が機能しなかったのか。突きつけられた課題は何か。復興に向けどのような視点が求められるのか。能登の教訓を企業のレジリエンスに生かすため、リスク対策.comがこの2カ月の取材から企業の対応を整理してお伝えします。
2024/02/27
-

被災者の声を傾聴し、ビジネス復興の糸口を探る
一般財団法人危機管理教育&演習センター(EEC、代表理事:細坪信二)は、2月17日~18日の2日間、令和6年能登半島地震で大きな被害を受けた七尾市や穴水町、輪島市の視察を行った。視察地は七尾市の和倉温泉や穴水町の漁港、輪島市の旅館やスーパーマーケットなど。今回から数回に分けて視察概要を紹介する(取材・執筆:EEC 川村丹美)
2024/02/27
-

いつどこの国でも大規模水害に見舞われる
近年の顕著な災害をもたらした大雨・洪水についても、一定程度は地球温暖化の影響があったことがわかってきています。そしてその大雨・洪水被害は、特定の地域だけでなく、世界中で発生しています。当然ビジネスへのダメージは大きく、特に製造や輸送への影響は甚大。それがいつどこの国でもあたり前に起こり得る状況になってきています。
2024/02/22
-

東京の大雪――2月の気象災害――
東京の大雪は2月に多い。これは、東京に大雪を降らせる南岸低気圧が2月に現れやすいことに起因している。今回は、東京の過去の大雪事例を観察し、留意すべきポイントを確認する。
2024/02/22
-

第243回: 地球規模の気候変動を踏まえつつ自然災害を総括した報告書(2024年版)
世界最大級の保険・再保険ブローカーであるAonが、1年間に発生した自然災害の被害規模や発生状況のトレンドなどをまとめた報告書の2024年版。2023年に起きた自然災害では、トルコ・シリア地震が死者数と経済損失の両方でトップ、保険金支払額でも2位となっている。
2024/02/21
-

製造を止めない全社的SCRMを展開
電気設備を製造・販売するパナソニックエレクトリックワークス社(大阪府門真市、大瀧清社長)は、発災時にも製品の製造を止めないサプライチェーンリスクマネジメントに取り組んでいます。重要な製品や部品を整理し、メーカーや製造拠点の詳細な情報まで把握。代替情報を加え、動き出しのスピードアップを実現しました。元日に発生した能登半島地震でも素早く対応し、製品製造に大きな影響はありませんでした。
2024/02/21
-

能登半島地震におけるBCP調査
元日に発生した能登半島地震で、北陸地方などに自社施設があり、かつBCPを策定していた企業のうち、「BCPが機能した」と感じている企業は、半数以下にとどまることが、リスク対策.comが実施したアンケート調査で明らかになった。従業員の規模別に分析したところ、1001人以上の企業では67.3%が機能したと感じているのに対し、100人以下は29.4%と大きく差が開いた。中小企業では、もともとBCPの策定率が大企業に比べ低いが、今回の調査では、BCPが実際に機能すると感じる「実効性」についても、大企業に比べ低い可能性があることを示唆するものとなった。
2024/02/19
-

支援行動と迷惑行為を分けたもの
正月に起きた能登半島地震に関してさまざまな情報が飛び交ったことは、前回も記述しました。今回は政治家や著名人も含めた一般の支援活動に関する情報を取り上げます。政府の対応からボランティア活動まで賛否両論渦巻く状態ですが、危機管理の視点から、冷静にそれらを俯瞰してみたいと思います。
2024/02/15
-

海外におけるESG/サステナビリティ情報開示の動向 ~日本企業が準備すべきこと~
3月のESGリスク勉強会の発表者は、海外におけるESGの動向や法規則に詳しい日本エンヘサ株式会社日本オフィス代表の田崎裕美氏です。
2024/02/08
-

能登半島地震でSNS情報はどう生かされたかネット情報空間の光と影
リスク対策.com の連載陣が、自身の記事や最近の事象を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドや注視するポイントを伝えるとともに、連載者と意見交換を行って、気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。
2024/02/07


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



