教育・ハウツー
-

企業と投資家の認識のズレを埋める
A社では、気候変動やグローバルサプライチェーンの寸断といった不確実性が高まる経営環境の変化に対応するために、数年前から多角化経営に着手していました。そのようななかで新型コロナウイルスの感染拡大が発生し、経済危機が発生。多角化経営の一環として社内で新規事業創出も始め、いくつかのイノベーションにつながる活動も端緒についたところです。しかし複数の投資家からさまざまな意見が出てきました。「投資家に対してきっちり説明して理解を得るように」との命を受けたBさんは、そのように説明すべきか頭を悩ませています。
2020/09/03
-

感染者の公表・非公表で悩む段階はもう過ぎた
地方の報道機関から「なぜ企業は社員の感染者を発表するのか」と聞かれ、企業からは「社員の感染を発表すべきか」と相談される。しかし、そこで悩んでいる段階はもう過ぎたのでは? いま、企業は何を視点にどのような情報発信活動を行えばよいのか、経済社会情勢の変化をふまえて解説します。
2020/08/31
-

感染予防に欠かせない消毒剤の適切な選択と扱い
COVID-19予防のためのワクチンが実用化されていない現在、予防手段として最も重要視されているのは、依然としてマスク、そして消毒剤です。しかし、消毒用アルコールの効果は一過性で、安全性は必ずしも万全ではなく、人によっては使用できない場合があることに注意しなければなりません。あらためて、消毒剤について考えてみます。
2020/08/31
-

災害関連死を防ぎ命と尊厳を守るために
社会保障審議会介護保険部会の新たな基本指針案で、市町村などが作成する介護保険事業計画の任意記載事項に「災害に対する備えの検討」が新設されました。内容はまだ不十分なものの、その意義は決して小さくありません。災害が要配慮者の心身を衰弱させることは明らか。これを機に、災害避難時にすべての国民の命と尊厳が守られる制度の議論が進むことを切望します。
2020/08/28
-

【Lesson2(5講義)】個別のリスクに強くなろう
従業員が最低限知っておくべきリスクに関する基本的な知識を、SNS、社内不正防止、災害時リスクなど具体的な場面をもとに学びます。解説者は、フォーサイトコンサルティング株式会社の五十嵐雅祥氏です。
2020/08/28
-

第8回 経営リスクに関する各種保険
フィナンシャルラインというカテゴリーに分類される保険種目について解説します。伝統的な賠償責任保険とは別のカテゴリーとして、フィナンシャルロス(経済的損失)のみを補償する保険カテゴリーです。日本では「経営リスク保険」と呼ばれています。
2020/08/24
-

温暖化の警告から30年経ち何が変わったか
気候科学者のジェームス・ハンセンが米上院公聴会で地球温暖化に警告を発してから30年余り。相変わらず二酸化炭素は排出され続け、気温はどんどん上昇しています。2000年に起こったITバブル不況、2008年のリーマン・ショック、国内では失われた20年からの回復や度重なる震災からの復興で経済の立て直しが優先され、気候問題は隅に追いやられた感が否めません。これまでの流れを振り返ります。
2020/08/20
-

今だから考えるインバウンド戦略の課題
新型コロナウイルスの影響により、日本のインバウンドは「一旦休止」を余儀なくされています。しかし、今だからこそ、政府主導のインバウンド政策を検証してみるべきでしょう。日本人がインバウンドにどう関与し、地域活性化、雇用機会増大という本来の効果をいかにもたらすかを考えるにはいいチャンス。現場の実態をふまえて解説します。
2020/08/19
-

第26回【最終回】:まとめ 防災活動の必須ポイント
これまで25回にわたり、中小企業が防災活動に取り組む際に押さえておくべきことを「これだけはやっておこう」という視点で説明してきました。最終回となる今回は、そのまとめとして防災活動の必須ポイントを説明します。
2020/08/19
-

ちょっと待って! その「セキュリティー警告」は本物?~パソコン編~
利用者を動揺させて金銭を騙し取る「サポート詐欺」。警告画面に慌てず、冷静に対応しましょう。
2020/08/17
-

材料3つで簡単おいしい炊き込みご飯!
みなさんこんにちは! 今回は材料3つとポリ袋で簡単につくれる炊き込みご飯を紹介します。備蓄してあるさば缶と生米、それに水だけでつくれる食べやすい1品。ぜひつくってみてください!
2020/08/07
-

マダニ咬傷だけでなく犬や猫からも感染
前回に続き、重症熱性血小板減少症候群 (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome : SFTS) について。これまで知られていなかった、死亡率の高いダニ媒介ウイルス感染病です。野外での活動が多くなるこれからの時期は、マダニに注意するとともに、動物からの感染にも気を付ける必要があります。
2020/08/07
-

【新連載】BCPの見直し迫るコロナそして温暖化
新型コロナウイルスにより、多くの企業がBCPの見直しに迫られました。ならばこれを一歩進め、本格的に「気候変動対策」にも着手してはどうか? それが本連載の趣旨です。「気候危機とは何か」「気候危機に適応する事業継続の考え方」「BCMによる持続可能社会への貢献」という3つのパートで、見直しのロードマップを考えます。
2020/08/06
-

防災備蓄を今のうちに見直していくべ
「防災備蓄ってどこに置いたらいいんですか?」。3年前に答えられなかった質問に、いまこそ赤プルさんが答えます。ポイントの一つは、ご家族がどういう生活スタイルなのか、もう一つはその家にどういう災害リスクがあるのか。つまり備蓄品の置き場を決めるには、この二つを確認しなければなりません。それはご家族の防災意識を高めるだけでなく、日々の生活環境の改善にもつながります。
2020/08/06
-

管理・監督者の安全観察力とコミュニケーション力を高めるプログラム
DSS サステナブル・ソリューションズ・ジャパンは、デュポンの安全トレーニング・プログラム「管理・監督者用STOP(Safety Training Observation Program)」を提供している。「リーダーは従業員の安全に責任を負う」という考えに基づき、管理・監督者が安全観察力やコミュニケーション力を高め、従業員と安全・不安全作業について建設的な話し合いができるようにするもの。安全を特別なイベントではなく日常の業務の一部とするための支援を提供する。
2020/08/05
-

避難の心得 基本編③水害・内水氾濫について
「令和2年7月豪雨」は、九州や中部地方などに甚大な被害をもたらしました。さらに今年は平年より長い梅雨となり、全国の広い範囲で水害が発生しています。雨のシーズンは秋まで続くうえ、梅雨明け後は局地的に降る強い雨が多くなる時期。「内水氾濫」への警戒と備えをぜひ確認しておいてください。
2020/08/05
-

第25回:防災活動の次に考えること その7
前回は、実際に訓練を行う場合の具体例として「被災状況の確認と安全確保」に関する訓練について説明しました。今回は「対策本部の立ち上げ」に関する訓練について考えます。
2020/08/05
-

コロナと共存する「転禍為福のBCP」とは?変化を見逃さず柔軟に危機対応、転換も恐れず
新型コロナウイルスの影響はグローバルサプライチェーン全体に及んでいます。供給の途絶だけでなく需要も落ち込み、現在なお出口が見えません。企業はこれからどのような戦略で事業を継続すればいいのか。6 月30 日に開催した危機管理カンファレンス基調講演で、名古屋工業大学の渡辺研司教授は「転禍為福」(禍転じて福と為す)のBCP のあり方を解説しました。
2020/08/04
-

生き残りをかけて明るい情報を発信する
危機時には明るい情報を発信してはいけないのかというと、そんなことはありません。現在は世界中が新型コロナウィルスで不安な状態にありますが、明るい情報発信に躊躇せず取り組むことが生き残りをかけたマネジメントになります。今回は、広げたい情報をどう発信したらよいかを解説します。
2020/07/30
-

第7回 グローバル企業にとっての賠償責任保険の留意点
賠償責任保険は各国により補償内容に違いがあります。不法行為法や民事訴訟法など背景となる法制度が国ごとに異なり、多様な法規制があるからです。さらに保険商品としての歴史が長く、それぞれの国の保険商品認可の歴史から国により多様な補償内容となっています。そのため、国際企業保険プログラム(GIP)を活用して国による補償の違いを埋める等の対策が必要となります。
2020/07/29
-

人権配慮ルールの周知と公表範囲の決定
新たに感染者やクラスターの発生が公表されるたびに、感染者やその関係者に対する懲罰的な言動が起こり、場合によっては謝罪にまで追い込まれてしまうといった事態が全国各地で垣間見られます。しかし、コロナウイルスに感染することは、不祥事ではありません。「油断をしたから」「本人に落ち度があったから」「この状況下で軽はずみな行動をしたから」といった非難には、断固たる姿勢で「そうではない」というべきです。
2020/07/28
-
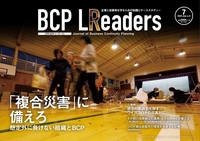
「複合災害」に備えろ
「月刊BCPリーダーズ」は災害や事故、感染症などの危機に対応し、事業継続をけん引する企業人(=BCPリーダー)に向けて、毎月1回お届けしているPDFテキストブックです。社内の回覧や共有、会議の参考資料などにもお使いください。
2020/07/23
-

レジリエンス向上のカギは中間管理職が握っている
個人に焦点を当ててレジリエンスの身につけ方を述べてきましたが、最終回は応用編です。いかにレジリエンスを発揮するかは、平たく言えば「いかにやる気を引き出すか」。一人ひとりの取り組みもさることながら、職場においては、レジリエンス向上の鍵となる人物がいることを忘れてはいけません。すなわち、中間管理層の人々です。社内の人々がレジリエントになれるかどうかは、中間管理層に左右されることが少なくないのです。
2020/07/22
-

第24回:防災活動の次に考えること その6
前回は、策定したBCPの実効性を向上させるために行う「訓練」の重要性と、それを準備するに当たってのポイントを説明しました。今回は、実際に訓練を行う場合の具体的な進め方を解説します。
2020/07/22
-

環境政策対応の鈍さが招く事業継続の危機その3
中国に進出した日系企業の事例を参考に、どのように環境対策を成功させるべきかを考察している本連載。ここ3回ほどは中国の法制度について解説しましたが、今回はまた具体事例をあげて考えます。環境政策に対する中国政府の真剣度を見誤らないこと、そのうえで早め早めに手を打つことが重要です。
2020/07/21




















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



