連載・コラム
-

-

-

-

-

-
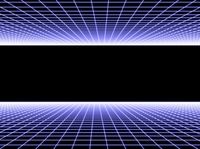
-

-

-

-

-

-

-

急務となっているカスタマーハラスメント対策
改正労働政策総合推進法第30条の2(通称、パワハラ防止法)が令和4年4月1日から中小企業にも適用されるようなり、パワハラ防止措置を講じることは、全ての事業主の義務となっています。最近は、ハラスメント防止措置の一環として、一般社員研修や管理職研修でハラスメント研修を実施する企業が増えており、私も講師を務める機会が増えていますが、パワハラ、セクハラなどの職場のハラスメントに加えて、「カスタマーハラスメント」に関する事項を研修内容に含めることを求められることが多くなっています。顧客等の著しい迷惑行為に悩む企業や労働者は少なくありません。そこで今回は、社会問題にもなっているカスタマーハラスメントについて解説します。
2022/06/07
-

-

-

-

-

-
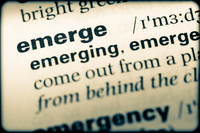
-

-
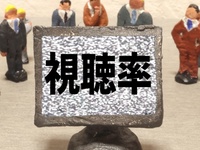
-

-

-

-







































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



