premium
-

AIの危機管理コラボルーム企業の知恵を集めるコミュニティ勉強会
初回は、危機管理に従事する実務担当者が、どのように生成AIを使っているかを、失敗談も含めて共有します。「自分は危機管理でこんなことを試してみたい」と思えるようになることが、今回のゴールです。
2026/01/29
-

サイバー攻撃対応BCP実践勉強会~NIST CSF 2.0で、止まらない会社をつくる~
【毎月1回30分のオンライン開催】サイバー攻撃対応BCP実践勉強会~NIST CSF 2.0で、止まらない会社をつくる~ この勉強会は、NIST CSF 2.0を軸に、サイバー攻撃に強いBCPを体系的に学ぶことを目的にしています。
2026/01/28
-
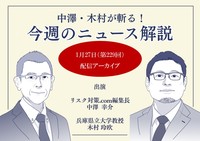
中澤・木村が斬る!【2026年1月27日配信アーカイブ】
【1月27日配信で取り上げた話題】知っておくべき今週のニュース10/大規模訓練から学ぶ「新・アクションカード」/山下記者のイチ押し危機管理プロダクツ
2026/01/27
-

突然の輸出規制による打撃地経学的対立を踏まえた転換
自由貿易が恩恵をもたらすと信じられていた時代が終わり、経済的優位性を持って規制や関税などの手段で他国に圧力かける地経学的対立が顕著になってきました。これまでの「低コスト・高効率」ビジネスモデルからの転換について、具体的な対応とともに解説します。
2026/01/26
-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

五六豪雪――1月の気象災害――
1980年12月12日、日本海を発達しながら北東へ進んだ低気圧が、翌13日には北海道の北へ進み、大陸から日本列島へ強い寒気が押し寄せ、日本海側の各地で一斉に雪が降り始めた。この冬初めての本格的な降雪である。これが、翌1981年3月にかけての一連の大雪の始まりであり、後に「五六豪雪」と呼ばれるようになった記録的豪雪の幕は切って落とされた。
2026/01/26
-

能動的なレジリエンス強化の必要性
企業は現在、気候変動の原因となっている温室効果ガスについて、事業活動からの排出削減に取り組んでいる。また、これまでのGHG排出の影響で変化した気候システムによる異常気象災害の拡大への対策を進めている。
2026/01/26
-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26
-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23
-

第10回 海外子会社経営リスク管理編(6)
今回は、中国の子会社における弊社の監査事例を紹介し、その事例をベースに、日本企業のガバナンス遂行上の課題を説明したいと思います。
2026/01/21
-
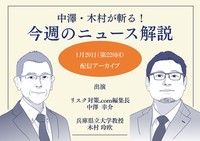
中澤・木村が斬る!【2026年1月20日配信アーカイブ】
【1月20日配信で取り上げた話題】知っておくべき今週のニュース10/グローバルリスク報告書を読む/基礎からわかる地震のメカニズムと予測
2026/01/20
-

不確実性の拡大に伴うレジリエンス強化
企業はこれまで経営の中心に据えてきた財務要素中心の短期利益至上主義から、非財務要素を考慮し中長期的に社会的価値と経済的価値の向上を両立させる方向へと舵を切り、サステナブル経営を推し進めようとしている。このような過程で、企業を取り巻く不確実性の高まりによる企業価値への変動幅の拡大に留意しなければならない。
2026/01/15
-
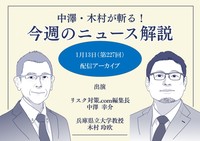
中澤・木村が斬る!【2026年1月13日配信アーカイブ】
【1月13日配信で取り上げた話題】知っておくべき今週のニュース10/2026年のグローバルリスク/毎熊典子の労務リスク対策
2026/01/13
-

オールハザード型BCPがもたらす組織変革
近い将来予想される連続災害、サイバー攻撃による事業の停滞、国際情勢や社会環境の変化による未知のリスクへの対応を余儀なくされ、企業はオールハザード型BCPの導入へと意識を向けています。が、新しいタイプのBCPも当然、内部監査を実施しなければなりません。従来のBCP監査の考え方や手法が大きく変わろうとしています。
2026/01/13
-

思い込み × 初動判断 × 情報が揃わない現実
能登半島地震(2024年)から2年が経ちました。今年は東日本大震災から15年、熊本地震から10年という節目でもあります。南海トラフ地震や首都直下地震への切迫感は、かつてないほど高まっています。 今回の訓練では、組織が判断を開始する瞬間に陥る「危機管理者の思い込み」を可視化します。
2026/01/12
-

第13回 高まるディープフェイクの脅威への対策
イメージ(Adobe Stock)ディープフェイクによる詐欺ディープフェイク*)は登場以来、目新しいフィルターや拡散するいたずら動画といったものから、深刻なビジネスリスクへと急速に変化してきた。
2026/01/11
-

第9回 海外子会社経営リスク管理編(5)
今回は実際の調査を基に行った日本企業と欧米企業のコーポレートガバナンスの比較を通じて、間接統治で本社・子会社が何を行うべきかについて見て行きたいと思います。
2026/01/07
-
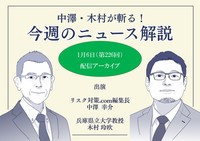
中澤・木村が斬る!【2026年1月6日配信アーカイブ】
【1月6日配信で取り上げた話題】知っておくべき今週のニュース10/携帯トイレの強度と防臭/2026年はサイバーBCP元年/リスクに効く心理学
2026/01/06
-

サイバー攻撃対応BCP実践勉強会~NIST CSF 2.0で、止まらない会社をつくる~
【毎月1回30分のオンライン開催】サイバー攻撃対応BCP実践勉強会~NIST CSF 2.0で、止まらない会社をつくる~ この勉強会は、NIST CSF 2.0を軸に、サイバー攻撃に強いBCPを体系的に学ぶことを目的にしています。
2026/01/06
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

第12回 企業リスクが大きくなる「米国各州の虚偽請求法」
多くの企業は「金銭や財産と引き換えに行政当局に虚偽の請求を行った」という事案を聞いたことがあるはずだ。例えば、2025年8月、CVSはマサチューセッツ州のメディケイドプログラムに対し、一般市民と比較して過剰請求していたという疑惑を解決するため、1225万ドルを支払うことになった。
2025/12/25
-

師走の特異な低気圧――12月の気象災害――
2004(平成16)年12月5日の早朝、東海地方や関東地方の沿岸部は南寄りの暴風に見舞われ、建物に多くの被害が発生したほか、交通機関などにも影響が生じた。この暴風をもたらしたのは、本州上を進んだ低気圧であった。
2025/12/24
-

環境変化に伴うビジネス機会の拡大と不確実性の拡大
ピーター・ドラッカーが、「経済的な活動は、現在の資源を不確かな未来に投入することであり、必然的に、企業は不確実性を管理する機能を必要とする 」と述べているように、企業活動には常に新たなビジネス機会の探索が必要である。しかし、それには不確実性が伴う。したがって企業は、いかにリターンの源泉としてリスクを取り、企業価値を持続的に高めてゆくかに腐心する存在である。
2025/12/24
-

ハラスメントの過剰反応が招く弊害堂々と指導できる企業に
「パワハラ」という単語にだけ反応し、指導が及び腰になることはリスクマネジメントの観点からも育成の観点からも組織文化の観点からも誤りです。基準を確認し、「堂々と指導できる企業文化」を目指しましょう。
2025/12/19


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



