premium
-

サプライチェーン強化による代替戦略への挑戦
包装機材や関連システム機器、プラントなどの製造・販売を手掛けるPACRAFT 株式会社(本社:東京、主要工場:山口県岩国市)は、代替生産などの手法により、災害などの有事の際にも主要事業を継続できる体制を構築している。同社が開発・製造するほとんどの製品はオーダーメイド。同一製品を大量生産する工場とは違い、職人が部品を一から組み立てるという同社事業の特徴を生かし、工場が被災した際には、協力会社に生産を一部移すほか、必要な従業員を代替生産拠点に移して、製造を続けられる体制を構築している。
2025/11/20
-

企業存続のための経済安全保障
世界情勢の変動や地政学リスクの上昇を受け、企業の経済安全保障への関心が急速に高まっている。グローバルな環境での競争優位性を確保するため、重要技術やサプライチェーンの管理が企業存続の鍵となる。各社でリスクマネジメント強化や体制整備が進むが、取り組みは緒に就いたばかり。日本企業はどのように経済安全保障にアプローチすればいいのか。日本企業で初めて、三菱電機に設置された専門部署である経済安全保障統括室の室長を経験し、現在は、電通総研経済安全保障研究センターで副センター長を務める伊藤隆氏に聞いた。
2025/11/17
-

第6回 海外子会社経営リスク管理編(2)
今回は、不正に弱い日本企業の経営管理上の特徴、直接統治の弊害と、日常管理における不正発見に役立つリスク予兆の見分け方を述べていきます。
2025/11/16
-

外部性への意識とサステナブル経営
われわれにとってどのような未来が望ましいのか、将来どのような社会にしてゆきたいのか、といった視点は社会課題の解決を考える際の起点となる。そして、今後の社会のあり様を描き、社会の進むべき方向性を明らかにしてゆく役割は、社会の構成員全員(国家、政治、企業、市民など)が担っている。また、具体的な課題解決においては、構成員全員がそれぞれの役割や機能を果たしてゆかねばならない。
2025/11/16
-

第9回 ビジネスには「4つの未来」が潜在する
地政学的緊張の高まり、テクノロジー導入の加速、そしてマクロ経済状況の変化により、経営幹部にとっては現在のビジネス環境がかつてないほど予測困難になっている
2025/11/16
-

中小企業のガバナンス
中小企業でも、求められるガバナンス領域は広がっています。ただし、ガバナンスの全てを社長が引き受けるのは、制度的にも精神的にも適切な方法ではありません。ひとたび不祥事が表沙汰になれば大規模に拡散され、ときに会社の存続に関わります時代。会社も社長も救える、ガバナンス着手について解説します。
2025/11/14
-

社長直轄のリスクマネジメント推進室を設置リスクオーナー制の導入で責任を明確化
阪急阪神ホールディングス(大阪府大阪市、嶋田泰夫代表取締役社長)は2024年4月1日、リスクマネジメント推進室を設置した。関西を中心に都市交通、不動産、エンタテインメント、情報・通信、旅行、国際輸送の6つのコア事業を展開する同社のグループ企業は100社以上。コーポレートガバナンス強化の流れを受け、責任を持ってステークホルダーに応えるため、グループ横断的なリスクマネジメントを目指している。
2025/11/13
-

リスクマネジメント体制の再構築で企業価値向上経営戦略との一体化を図る
企業を取り巻くリスクが多様化する中、企業価値を守るだけではなく、高められるリスクマネジメントが求められている。ニッスイ(東京都港区、田中輝代表取締役社長執行役員)は従来の枠組みを刷新し、リスクマネジメントと経営戦略を一体化。リスクを成長の機会としてもとらえ、社会や環境の変化に備えている。
2025/11/12
-

入国審査で10時間の取り調べスマホは丸裸で不審な動き
ロシアのウクライナ侵略開始から間もなく4年。ウクライナはなんとか持ちこたえてはいるが、ロシアの占領地域はじわじわ拡大している。EUや米国、日本は制裁の追加を続けるが停戦の可能性は皆無。プーチン大統領の心境が様変わりする兆候は見られない。ロシアを中心とする旧ソ連諸国の経済と政治情勢を専門とする北海道大学教授の服部倫卓氏は、9月に現地視察のため開戦後はじめてロシアを訪れた。そして6年ぶりのロシアで想定外の取り調べを受けた。長時間に及んだ入国審査とロシア国内の様子について聞いた。
2025/11/11
-

地政学リスク×重要部品停止×連鎖する生産停止
イメージ(Adobe Stock)オランダの1社が安全保障上の懸念で事業停止となったことで、日本の自動車メーカーが北米で減産に追い込まれる事態が発生しました。「うちは自動車業界じゃないから関係ない」と思われた方、ちょっと待ってください。
2025/11/10
-

第5回 海外子会社経営リスク管理編(1)
今回は「海外子会社の経営リスク管理とは(1)」として典型的な経営リスクの一つである不正事例と不正発生の原因を考えていきます。
2025/11/10
-

第二次トランプ政権 未曽有の分断の実像
第二次トランプ政権がスタートして早や10カ月。「アメリカ・ファースト」を掲げ、国益最重視の政策を次々に打ち出す動きに世界中が困惑しています。折しも先月はトランプ氏が6年ぶりに来日し、高市新総理との首脳会談に注目が集まったところ。アメリカ政治に詳しい上智大学の前嶋和弘教授に、第二次トランプ政権のこれまでと今後を聞きました。
2025/11/05
-

第59回:来たか、デジタル暴風雨
この夏、命の危険に関わる暴風雨という言葉を何度も聞く一方、ビジネス界にも強烈なデジタル暴風雨が襲いかかり、復旧の見通しが立たないという報道が増えています。社内の焦燥感は推察するに余りあり、そういう心理状態では経営層も担当者も委縮してしまうのではと危惧します。そこで、前に進む勇気を与えてくれるアイデアを考えてみました。
2025/10/30
-

事業を止めるサイバー脅威と対峙せよ
サイバー攻撃による大企業の事業停止が頻発。近年はERP(統合業務システム)の導入で、システムの一部に障害が発生すると影響範囲が広範に及びます。SIerなど外部への依存度も高まるため、社内にセキュリティ人材やスキル・哲学、業務フローの理解が欠けているとリスクをスルーしかねません。ERPのリスク、障害対策に向き合うときです。
2025/10/29
-

多発するランサムウェア被害狙われる制御システム
工場やインフラ設備などの制御システムであるOT(Operational Technology)の代表格である、製造業でランサムウェア被害が明らかになりました。9月29日、アサヒグループホールディングスが入出荷のシステム停止などを公表しました。個人情報が流出した可能性があるといいます。なぜ工場や社会インフラ設備を狙うサイバー攻撃が最近多発しているのかを、攻撃者の視点も含め解説します。
2025/10/27
-

大正6年の高潮災害――10月の気象災害――
東京の気象資料を見ていて、気になるデータがある。海面気圧の最低記録が、1917(大正6)年10月1日に記録されているのである。100年以上も破られていないこの記録を生んだ気象じょう乱は、関東地方を襲った台風であった。
2025/10/27
-

環境変化への対応力の強化
企業を取り巻く社会的価値観が大きく変化している。企業はまずその変化の本質を把握しなければならない。なぜなら、企業活動と社会の価値観にギャップが生ずれば企業の存続を揺るがし、持続的成長は望めないからである。
2025/10/26
-

サプライチェーン攻撃×物流基盤停止×連鎖する事業停止
1社がサイバー攻撃にあったことで、競合他社を含めた業界全体が物流の停止に追い込まれるような事態が発生しました。「うちは物流会社じゃないから関係ない」と思われた方、ちょっと待ってください。あなたの会社の商品は、どうやって顧客に届いていますか?
2025/10/25
-
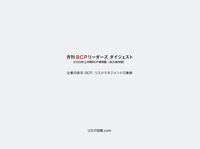
月刊BCPリーダーズ2025年上半期事例集【永久保存版】
リスク対策.comは「月刊BCPリーダーズダイジェスト2025年上半期事例集」を発行しました。防災・BCP、リスクマネジメントに取り組む12社の事例を紹介しています。危機管理の実践イメージをつかむため、また昨今のリスク対策の動向をつかむための情報源としてお役立てください。
2025/10/24
-

第8回 ややこしい米国の「従業員のソーシャルメディアでの政治的発言」
多くの人々が政治的に重要な問題について意見を表わす上で、ソーシャルメディアは公共の場となっている。中東紛争、ロシアとウクライナの進行中の戦争、アメリカの政治、政治家の暗殺など、話題が何であれ、従業員はX(旧Twitter)・Facebook・Instagram・TikTokなどのプラットフォームを利用して意見を共有することが増えている。
2025/10/24
-

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献
地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。
2025/10/20
-

第4回 リスクの基本特性とバイアスの排除
コラム第4回は、VUCAの時代のリスク対応に求められるリスク感性を中心に述べていきます。
2025/10/20
-
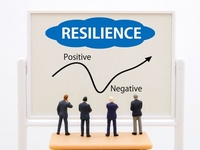
BCPは時代の要求に追いついているか?
前々回、BCPは「守り」から「攻め」へ転換していると申し上げました。BCPは企業のサスティナビリティ戦略の一環として、価値創造のうえで重要な要素。複合災害を含め予測困難なリスクにも対応できなければなりません。オールハザード型BCPが不可欠ですが、いまだ課題が多いのが実情です。あらためてオールハザード型BCPの課題を整理します。
2025/10/15
-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく
スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。
2025/10/14
-

上司と部下のデートはもうできない!?
CEOの不倫・恋愛スキャンダルはときに世間の耳目を集めます。「不倫がバレて」はよく聞くところですが、最近の米国では社内恋愛を報告していなかったとして退任に追い込まれる事例も。いわゆる「普通の恋愛」を含め、職場内外での親密な関係を制限する動きが広まっているためです。今回は、CEOの私生活が企業のリスクとなる問題をまとめます。
2025/10/14


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



